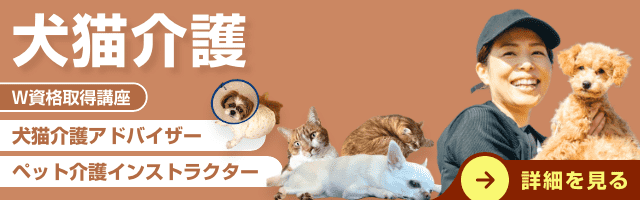犬の繁殖をするには?交配の適齢期や方法と注意点
記事更新日:2024年9月4日犬の繁殖は慎重に行う必要があります。
適切な年齢や健康状態の雌雄を選び、計画的な交配を行うことが重要です。
雌犬は通常6か月齢以降に初回発情を迎えますが、1歳前後が最適な初交配時期とされています。
一方で雄犬は8か月齢以降に繁殖能力を発揮するようになります。
不適切な交配は、子犬の健康と遺伝的リスクを高める可能性があるため、獣医師の助言を得ながら、責任を持って行うべきです。
犬の繁殖を進める場合は、出産に適した時期や発情の時期についてしっかり配慮する必要があります。そういったポイントを意識しないと、健康的な子犬を生めない可能性も出てきてしまいます。元気な子犬を育てるためには、母体にしっかり配慮することが必要不可欠です。
犬の繁殖では具体的にはどういったことについて配慮すればよいのでしょうか。出産は命にかかわる重大なことですから、慎重に気を使う必要があります。今回は犬の繁殖の基本とともに、適齢期や注意点について説明します。

目次
犬の繁殖の適齢期
犬の繁殖の適齢期は以下の通りです。 ● メス犬は生後6~12か月齢が初発情期 ● オス犬は生後6~14か月齢が性成熟期 ● 1回目の発情期は精子の質が十分ではない場合がある こちらを順に解説していきます。
メス犬は生後6~12か月齢が初発情期
犬の繁殖におけるメス犬の適齢期は、生後6か月齢から12か月齢前後が初発情期に当たります。 犬の発情は、毎年平均2回、約6か月間隔で訪れる生理現象です。 初回発情は通常生後6か月齢前後に始まりますが、個体差が大きく、生後5か月齢から10か月齢までの幅があり発情期には、排卵と受精の準備が整うため、この時期が初交配の適切な時期と考えられています。 しかし、12か月齢を過ぎると発情周期が乱れる可能性があるため、その前に交配を行うことが望ましいとされています。 また、初産の場合は13〜18か月齢が最適とされ、それ以前の交配は避けるべきでしょう。 幼すぎる年齢での出産は、母犬や子犬の健康リスクが高くなるからです。 適切な時期に交配を行えば、母犬の成熟した子宮と子犬の健康な発育が期待できます。 一方、早すぎるか遅すぎる交配は、生殖能力の低下や、母犬や子犬への悪影響が懸念されます。 経験の浅いブリーダーは獣医師に相談するなどして、慎重に行動することが重要です。
オス犬は生後6~14か月齢が性成熟期
犬の繁殖におけるオス犬の適齢期は、生後6か月齢から14か月齢前後が性成熟期に当たります。 オス犬の性成熟は、メス犬に比べてやや遅れる傾向があるのです。 一般的に、生後6か月齢頃から徐々に精子の産生が始まり、8か月齢前後で初めて交配が可能になるでしょう。 しかし、完全な繁殖能力を発揮するのは12か月齢前後からとされています。 この時期になると、オス犬の性行動や性器の発達が顕著になり、メス犬に対する興味や求愛行動が見られるようになります。 ただし、14か月齢を過ぎると、しばしば攻撃性や支配行動が強まる傾向にあるため、この年齢以降の交配は避けるべきです。 適切な時期に交配を行うことで、オス犬の健康な精子と、メス犬の受精能力が最大限に発揮されます。 一方、早すぎる交配は、オス犬の精子の質や量が不足する可能性があり、遅すぎる交配は、オス犬の攻撃性などの問題行動が懸念されます。 ですので、ブリーダーは犬の性成熟過程を理解し、最適な交配時期を見極める必要があるでしょう。 経験の浅いブリーダーは獣医師に相談するなどして、慎重に行動することが重要です。
1回目の発情期は精子の質が十分ではない場合がある
犬の繁殖においては、メス犬の初回発情期と、オス犬の性成熟期がそれぞれ重要な適齢期となります。 しかし、初回発情期のメス犬と、初期の性成熟期のオス犬では、繁殖能力に制限があることにも留意が必要です。 メス犬の初回発情期は通常6〜12か月齢ですが、この時期は子宮や卵巣の発達が完全ではなく、排卵や受精能力が未発達な場合があり、そのため、初回発情期の交配は避けるのが賢明です。 同様に、オス犬の性成熟期はおおむね6〜14か月齢ですが、特に8〜12か月齢の間は精子の質や量が不安定な状態にあり、この時期の交配では、子犬の健康や遺伝的な問題が生じる可能性があります。 適切な繁殖には、メス犬が13〜18か月齢、オス犬が12か月齢以降の交配が望ましいとされています。 この年齢になれば、雌雄ともに生殖能力が安定し、健康な子犬を得られる確率が高くなるでしょう。
犬の健康状態の確認
犬の健康状態の確認は以下の通りです。 ● 両親犬の遺伝的素質や健康状態を確認 ● 感染症や遺伝病のスクリーニングを実施 ● 繁殖能力性格外観などの適性を評価 こちらを順に解説していきます。
両親犬の遺伝的素質や健康状態を確認
犬の繁殖において、両親犬の健康状態と遺伝的素質を確認することは非常に重要です。 遺伝的な素因や疾患は子犬に伝わる可能性があるため、慎重な配慮が必要不可欠です。 まずは、両親犬の健康診断を実施し、明らかな疾患や異常がないことを確認する必要があります。 遺伝性の関節疾患、眼疾患、心臓病、神経疾患など、多くの遺伝性疾患が犬種によって報告されています。 これらの疾患を持つ両親から生まれた子犬は、高い確率でその疾患を受け継ぐことになるでしょう。 次に、両親の体格、気質、行動特性などの遺伝的素質を評価しましょう。 優れた遺伝的素質を持つ両親から生まれた子犬は、より高い可能性で健康で優れた特性を備えることが期待できます。 ブリーダーはこうした両親の情報を慎重に検討し、最終的に交配の可否を判断する必要があります。 遺伝的問題のある個体同士の交配は避け、健康で優秀な親犬から子犬を生み出すことが重要です。 適切な両親選択と健康管理により、健康で質の高い子犬の誕生が期待できるのです。
感染症や遺伝病のスクリーニングを実施
犬の繁殖において、感染症や遺伝性疾患のスクリーニングは重要な健康管理の一環です。 これらの疾病が子犬に伝播されると、健康被害や育成上の問題が生じる可能性があるため、十分な予防措置が必要となります。 まず、両親犬に対して各種感染症のワクチン接種歴や抗体検査を行うことが大切です。 保菌状態にある親犬から生まれた子犬は、深刻な感染症に陥る危険性があるため、適切なワクチン接種など対策が求められ、遺伝性疾患のスクリーニングも重要です。 ブリーダーは、両親の体格、行動特性、既往歴などから、遺伝性関節疾患、眼疾患、神経疾患などのリスクを事前に評価します。 必要に応じて、専門の獣医師による遺伝子検査や特定の疾患に関する検査を実施し、リスクの高い個体同士の交配を回避することが望ましいです。 このように、感染症と遺伝性疾患のスクリーニングを丁寧に行うことで、健康で質の高い子犬の誕生につなげることができるでしょう。 ブリーダーの責任と、子犬の幸せのためにも、十分な健康管理が求められるのです。
繁殖能力性格外観などの適性を評価
犬の繁殖において、両親の健康状態だけでなく、繁殖能力や性格、外観などの適性評価も重要です。 これらの要素を総合的に検討し、より優れた子犬の誕生につなげることが求められます。 まず、両親の繁殖能力を確認します。 メス犬の発情サイクル、受胎率、産子数などを見極め、良好な繁殖実績があるかを評価します。 オス犬についても、精子の質や数、交配時の行動など、繁殖力に関する指標を慎重に確認する必要があるでしょう。 次に、両親の性格や行動特性も評価の対象となります。 温順で協調性のある個体は、子犬の性格形成に好影響を及ぼしますが、攻撃性や神経質な個体からは望ましくない性質が遺伝される可能性があります。 見栄えの良い個体から生まれた子犬は、審査会などでの評価が高くなる傾向にありこれらの繁殖適性を総合的に評価し、健康で優れた特性を備えた親犬を選抜することで、質の高い子犬の誕生が期待できるでしょう。 ブリーダーには、丁寧な検討と適切な判断が求められるのです。
犬の交配の方法
犬の交配の方法は以下の通りです。 ● 自然交配と人工授精の2通りがある ● 自然交配は監視下で行い適切な時期を見極める こちらを順に解説していきます。
自然交配と人工授精の2通りがある
犬の交配には、自然交配と人工授精の2つの主要な方法があります。 それぞれに長所と短所があり、適した状況に応じて使い分ける必要があり、自然交配は、メス犬とオス犬を直接合わせる伝統的な方法です。 雌雄の本能的な求交行動を利用することで、自然な受胎が期待でき、特別な設備を必要としないため、小規模な繁殖に適しています。 ただし、雌雄の体格差が大きいと事故のリスクがある点や、発情サイクルの管理が必要な点が課題となるでしょう。 一方、人工授精は、オス犬の精液を採取し、これをメス犬に注入する方法があります。 繁殖計画の柔軟性が高く、遠隔地の個体同士の交配も可能になり感染症や遺伝的リスクの管理にも効果的です。 ただし、専門の設備と技術が必要で、コストがかかるのが難点です。 このように、自然交配と人工授精には一長一短があります。 ブリーダーは、両親の健康状態、繁殖目的、経済的な条件などを総合的に勘案し、最適な交配方法を選択する必要があります。 適切な交配管理により、健康で質の高い子犬の誕生につなげることができるのです。
自然交配は監視下で行い適切な時期を見極める
犬の自然交配を行う際は、メス犬の発情サイクルを慎重に監視し、適切な時期に交配を行うことが重要です。 メス犬の発情は通常2〜3週間続きますが、受胎可能な期間は1週間ほどに限られます。 ブリーダーは、メス犬の外見や行動の変化から発情サイクルを把握し、最適な交配タイミングを見極める必要があり、交配前には、両親犬の健康状態を十分に確認しましょう。 感染症や遺伝性疾患のリスクがないかを慎重に評価し、問題がある場合は交配を中止するべきです。 また、体格の差が大きい個体同士の組み合わせは事故のリスクが高いため、避けるようにしましょう。 実際の交配は、人間が監視下で行いメス犬の積極的な求交行動や、オス犬の交尾行動を確認しながら、順調に交配が行われているかを確認します。 必要に応じて、介助や介入を行い、安全性を確保する必要があり、慎重な管理の下で行われる自然交配は、健康で活力のある子犬の誕生につながるのです。 ブリーダーの十分な経験と配慮が不可欠です。
妊娠・出産管理
妊娠・出産管理は以下の通りです。 ● 妊娠期間の食事運動ストレス管理 ● 分娩日の予測と立ち会い必要な介助 ● 子犬の体調チェックと育成環境の整備 こちらを順に解説していきます。
妊娠期間の食事運動ストレス管理
犬の妊娠・出産の管理においては、メス犬の健康管理が非常に重要です。 特に、妊娠期間中の食事、運動、ストレス管理に細心の注意を払う必要があり妊娠期間中のメス犬の食事管理では、高品質な犬用フードを適量与え、必要な栄養素を確保することが不可欠です。 カルシウムやたんぱく質、ビタミンなどが不足すると、母犬や子犬の健康に悪影響を及ぼすことがあります。 また、過剰な肥満は難産を招くリスクがあるため、適切な摂取量に留める必要があるので運動については、適度な散歩などが推奨されます。 過度な運動は避け、母犬ができるだけストレスなく休息できるよう配慮しましょう。 ストレスの蓄積は流産や難産の原因にもなりかねません。 そのため、穏やかな環境づくりや優しい対応など、メス犬の心身の安定を図ることが重要です。 さらに、定期的な獣医師による健康診断も欠かせません。 このように、母犬の健康管理に細心の注意を払うことで、健康な子犬の誕生につなげることができるのです。
分娩日の予測と立ち会い必要な介助
犬の妊娠・出産管理において、分娩日の予測と立ち会いは非常に重要です。 適切な介助を行うことで、母犬と子犬の健康を守ることができます。 分娩前には、母犬の行動や体調の変化に注意を払いましょう。 食欲の低下、体温の下降、落ち着きのなさなどが現れたら分娩の開始です。 分娩の立ち会いの際は、必要に応じて適切な介助を行います。 正常な分娩経過では、無理に介入せず様子を見守りますが、難産の兆候がある場合は獣医師に相談し、医療的処置を検討します。 子犬の挟まりや子宮の収縮不全など、問題が生じた際は迅速に対応することが重要です。 分娩後も、子犬の状態や母犬の授乳行動を注意深く観察し、問題がある場合は獣医師に相談しましょう。 こうした丁寧な管理により、健康な子犬の誕生と母犬の安全を確保することができるのです。
子犬の体調チェックと育成環境の整備
犬の妊娠・出産の管理では、子犬の健康状態の確認と育成環境の整備も欠かせません。 子犬の体調チェックは、生後すぐから定期的に行う必要があります。 体重の増加、呼吸・排せつの状況、眼・耳の清潔さ、毛並みの状態など、様々な指標を確認し、異常がないかを確認し異常が見られる場合は即座に獣医師に相談し、適切な処置を行う必要があります。 また、子犬の発育にとって最適な環境を整備することも重要です。 温度や湿度、換気、清潔さなどを適切に管理し、コンパクトで安全なスペースを用意しましょう。 必要に応じて保温用品を設置し、子犬が快適に過ごせるよう配慮します。 子犬は母犬の乳汁を主な栄養源としますが、生後4週間以降は徐々にフード摂取に移行していきます。 この時期の食事管理にも十分注意を払い、子犬の成長に合わせて適切な量と質のフードを与えることが大切です。 人や他の動物との接触機会を設け、ストレスなく慣れていけるよう働きかけることで、健康で社会性のある犬の成長が期待できます。 子犬の健康管理と最適な育成環境の整備は、健全な成犬へと導く上で欠かせない要素です。
倫理的配慮と法的規制
倫理的配慮と法的規制は以下の通りです。 ● 過剰繁殖の防止と健康な子犬の誕生を重視 ● 地方自治体の条例や関連法規を遵守 ● 品種団体の倫理規定に沿った適切な管理 こちらを順に解説していきます。
過剰繁殖の防止と健康な子犬の誕生を重視
犬の妊娠・出産管理においては、倫理的配慮と法的規制を十分に考慮する必要があります。 まず、無計画な繁殖を防ぐことが重要です。 過剰繁殖は、多くの子犬の健康と幸せを脅かす可能性があるでしょう。 そのため、メス犬の出産適齢期や体調、家庭環境などを慎重に検討し、無責任な繁殖を避けることが求められます。 また、動物愛護の観点から、子犬の健康的な育成を最優先にする必要があり、犬の命は尊重されるべきであり、適切な飼育環境の確保や医療的ケアの提供などが不可欠です。 問題のある子犬の販売や虐待には厳しい姿勢で臨む必要があります。 さらに、関連する法規制にも留意する必要があり多くの自治体では、犬の登録制度や飼育に関するルールが設けられているのです。 プロの専門家だけでなく、一般の飼い主にも、倫理意識と社会的責任感が求められます。
地方自治体の条例や関連法規を遵守
犬の妊娠・出産管理においては、地方自治体の条例や関連する法規の遵守が重要です。 これらの規制は、動物の福祉と地域社会の安全を守るための重要な枠組みとなっています。 まず、多くの自治体では動物の登録制度を設けており、飼い主は犬の登録を行う必要があり登録することで、犬の所有者が明確になり、適切な飼養管理が期待できるでしょう。 また、狂犬病予防法に基づき、定期的な予防接種の実施も義務づけられています。 さらに、自治体によっては、犬の飼養に関する様々な条例が制定されています。 犬の繁殖や販売、引取り、飼養環境の基準など、多岐にわたる規制が設けられている場合があり、条例を遵守し、適切な対応をすることが求められるでしょう。 加えて、動物愛護法や動物の保護及び管理に関する法律など、国の法規制にも留意する必要があります。 これらの法律では、無秩序な繁殖の防止や虐待の禁止など、様々な義務が定められています。 飼い主一人一人が、これらの規制を正しく理解し、実践していくことが重要なのです。
品種団体の倫理規定に沿った適切な管理
犬の妊娠・出産管理においては、品種団体の倫理規定に沿った適切な管理が重要です。 多くの犬の品種団体では、健全な犬の育成と飼養管理に関する倫理規定を定めているのです。 これらの規定には、繁殖犬の選定、繁殖回数の制限、子犬の健康管理や譲渡条件など、様々な指針が示されています。 品種団体の倫理規定に沿って適切に管理することで、無秩序な繁殖を防ぎ、遺伝的な問題を抑制することができます。 また、子犬の健康と福祉を最優先に考えた飼養環境の確保や、責任ある譲渡が期待できるでしょう。 倫理規定への違反や品質管理の不備は、ペットショップや個人の無計画な繁殖と同様に、問題を引き起こす可能性があるので飼い主はもちろん、専門家や関係者全員が、品種団体の倫理規定を理解し、遵守する必要があります。
交配に最適な時期とは?

交配を行うには適した時期があります。安全に健康的な交配を行うためにはとても重要なことなので、時期に配慮した交配を行いましょう。
出産するのに適した年齢は2~5歳くらい
犬は生後6~12ヶ月で初めての発情期を迎えるのが普通です。交配することができるのは2回目以降ですが、犬が出産するのに適している年齢は2~5歳くらいだといわれています。この年齢の間で出産することは、親となる犬と子犬の健康をしっかり確保するためにとても大切です。時期を誤ると、母体に負担がかかったり子犬にも影響が出たりする可能性があります。
1歳程度でも6歳を過ぎてからでも問題がある
犬は1歳程度のうちはまだ遺伝病をもっているかどうか判断することができません。そのため、1歳で交配してしまうと、遺伝病をもった犬が生まれてきてしまう可能性も否定できません。また、6歳を過ぎた犬が出産するとなると、母体への負担が大きくなってしまいます。犬は5歳の時点で、人間でいう40歳くらいになっています。こういったことを考えれば、やはり6歳での出産は避けたほうがよいでしょう。加齢により体力がなくなってきてからの出産は、難産になることが多いです。
メス犬の発情と排卵
交配を行う際は、メス犬の発情や排卵の周期についても理解しておくことが必要です。発情や排卵の周期を上手く利用して妊娠を目指しましょう。
メス犬の発情周期は6~12ヶ月
メス犬が発情する周期は、6~12ヶ月だといわれています。周期というのは、一度発情してから再び発情するまでの期間のことです。メス犬はこの間に発情前期、発情期、発情休止期、無発情期という4つのサイクルを経ます。発情するたびにこれを繰り返していきます。そのため、年2回程度発情期を迎えることが多いですが、年1回だとしても犬に何か問題があるわけではありません。
発情による出血から9日目くらいに排卵
犬は発情前期に入ると陰部から出血が起こります。出血は発情期に入るとだいぶおさまり、発情休止期に入ると完全に止まります。発情による出血が起きたらその9日目頃に排卵が起きるのが一般的です。卵子が受精できる状態になるまではさらに2日かかるとされています。そして、その卵子が受精できる期間は約2日ほどです。この期間中に受精させることで交配を進めます。 なお、犬は発情前期になると外陰部が硬くなり、発情期になるとこれがピークに達します。そして排卵するとこれが小さくなるので、外陰部が小さくなった翌日または翌々日あたりが交配を行うチャンスの最終日ということになるでしょう。交配を行う際はメス犬の様子をよく観察しながら適した日を見極めることが重要です。計画的に繁殖を進めていきましょう。
交配の基本パターン
犬の交配にはさまざまなパターンが考えられます。交配を行う際はそれぞれの特徴についてよく理解しておくことが必要です。
インブリーディング
インブリーディングとは、「近親繁殖」のことです。具体的には直近の5代をみて血縁関係のある交配のことをさしており、さらに以下のものがあります。
*ラインブリーディング
ラインブリーディングは「系統繁殖」と呼ばれるもので、3~5代の間に同一の犬が2回以上編入されることです。近親交配によって現れる難点をおさえながら、特定の特徴を維持するために行われてきた方法です。弱体や奇形の子犬が生まれる可能性が低いため、その犬の系統の長所を安定的に継承したい場合に活用されます。
*インセスチュアブリーティング
インセスチュアブリーティングは「極近親繁殖」といわれるもので、親子や兄弟姉妹などかなり近い血縁関係の中での交配をさしています。ラインブリーティング同様、系統を保つために行われることがありますが、血縁が近すぎることで能力の低下を招いたり、奇形を引き起こしたりする可能性があります。
アウトブリーディング
アウトブリーディングは「異系繁殖」のことで、5代のうちに血縁関係がみられない交配のことです。遺伝子が遠いとより免疫力などが高くなるとされており、それを目指して行われる交配のことです。
インターブリーディング
インターブリーディングは「変種間繁殖」のことで、同一種内で変種どうしを交配させるものです。例をあげると、ロングヘア―ダックスフントとスムースダックスフントの掛け合わせなどがこれにあたります。
アウトクロッシング
アウトクロッシングは「異種繁殖」のことで、種類の異なる2つの犬を掛け合わせる交配のことをいいます。
繁殖時の注意点
犬の交配を進めるときは注意すべきこともあります。健康的な子犬を育てるためにも、きちんと確認をとることが重要です。
交配前に必ず獣医師の診断を受けること
交配を行うなら、メス犬が出産適齢期に入ったときに必ず健康診断を受けに行きましょう。これはメス犬に病気がないかどうかを確認するためです。寄生虫や遺伝病のほか、生殖器系の病気があると、そのまま妊娠に入るのは危険です。遺伝病をもっている場合、生まれてくる子犬にもそれが遺伝する可能性があります。交配を希望するなら、きちんと母体の安全を確認した上で交配を進めるようにしてください。
インブリーディング(近親交配)に注意
繁殖を行う際は、インブリーディングに注意する必要があります。インブリーディングを行うと「近交退化」が起こる可能性があります。「近交退化」とは生まれてくる子犬にさまざまな欠点が生じることをいいます。オーバーブリードという呼び方をする場合もあります。具体的には、生殖能力が低下した犬が生まれたり、てんかんなどの病気をもった犬が生まれやすくなったりします。もちろん、インブリーディングではなくても何かしらの問題を抱えた子犬が生まれる可能性がないわけではありません。しかし、インブリーディングではその可能性が非常に高くなる傾向があるため、そういった交配はなるべく避けるようにすべきだといえます。
犬の繁殖はきちんと知識を身に付けたうえで行うこと

犬を繁殖させるためには、メス犬の妊娠可能な時期についてきちんと考慮する必要があります。そういった点を理解していないと、メス犬に過度な負担がかかることも予想されるので要注意です。健康的な子犬を育てるためにも、母体の健康状態に気を使ってきちんとした配慮を行わなければなりません。
なお、犬も妊娠すれば人間のようにつわりなどの症状に苦しむこともあります。妊娠は犬にとって命がけで行う重大なことです。母体への影響をきちんと考えつつ、なるべく過度な負担がかからないように配慮する必要があります。犬の繁殖を進めるときはきちんと責任をもって、犬を支えてあげられるように心掛けましょう。
まとめ
犬の繁殖は慎重に行うことが大切であり犬の年齢や健康状態をしっかり確認し、計画的な交配を行うことが重要になってきます。 メス犬は通常6か月齢以降に初回発情を迎えますがオス犬は8か月齢以降に繁殖能力を発揮するようになるでしょう。 不適切な交配は、子犬の健康と遺伝的リスクを高める可能性があるため、獣医師の助言を得ながら、責任を持って行うべきです。 安易な購入や無計画な繁殖を避け、子犬の健康を考えることが何よりも大切なのです。
- 通信講座のSARAスクール編集部
-
心理カウンセラー資格やリンパケアセラピスト等の体系資格、食育資格などを扱うSARAスクール編集部が運営するコラムです。主に女性向けのキャリアアップやスキル習得を目的とした講座が多く、家事や育児と両立しながら学べる環境が整っています。資格取得を目的とした講座も充実しており、仕事や日常生活に活かすことが可能です。