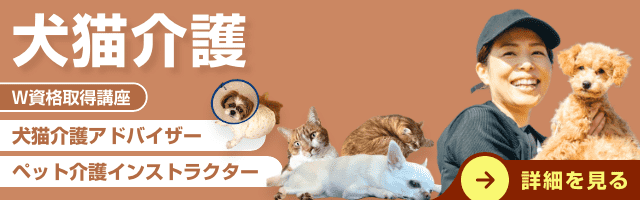犬の分離不安症とは?症状の原因や対策について解説!
記事更新日:2024年9月8日犬は、飼い主と過ごす中で「分離不安症」という症状を引き起こすことがあります。この分離不安症とは、具体的にどのような症状なのでしょうか。分離不安症は、状況によってどの犬も発症する可能性があります。そのため、しっかりと症状について理解しておいたほうがよいでしょう。
今回は、犬の分離不安症について説明します。症状の原因や対策についてもあわせて解説するので、犬の分離不安症に対する理解を深めるために役立ててください。

目次
犬の分離不安症とは?
犬の分離不安症とは、どのようなものなのでしょうか。分離不安症とは、犬が飼い主と離れることによって強い不安感に襲われる症状をさします。飼い主と離れることが不安で仕方ない状態になり、精神的パニックを起こしてしまうのです。分離不安症になると、犬は精神的にも肉体的にも不調になってしまいます。そのため、愛犬が分離不安症になってしまった場合は、早めの対処が必要だといえます。
分離不安症の症状
犬の分離不安症は、具体的にどのような症状なのでしょうか。分離不安症の症状としては、さまざまなものがあります。分離不安症に対処するためには、分離不安症の症状について詳しく把握しておく必要があるでしょう。ここでは、分離不安症の症状について詳しくみていきます。
基本的な症状
分離不安症の基本的な症状としては、飼い主が出掛けようとするとソワソワし出すことがあげられます飼い主の後をついて回ったり、飼い主の外出を知ると吠えたりします。また、実際に飼い主が出掛けた後は、飼い主がいない間に家の中で物を壊したり、トイレではない場所で排泄したりすることもあります。さらには、日常的に食欲不振となってしまうこともあるようです。いずれも、飼い主にとっては困った状態になるといえます。
重症の場合
分離不安症は、重症化するとさらに異なる症状が出ます。たとえば、暴れまわったり騒いだりして家具を壊すこともあります。さらに、自虐的な行動をとってしまうこともあります。血が出るまで体を舐めたり噛んだりする場合もあります。加えて、体の毛が抜けてしまうこともあります。重症化すると、見てみぬふりはできない状態になってしまうでしょう。重症化する前の早い段階で適切な対処をすることが大切です。
分離不安症になる原因
犬の分離不安症は、飼い主と離れることを必要以上に不安に思ってしまうものです。この症状は、どのようなことが原因となって起きるのでしょうか。基本的には、生活環境や育て方が原因となっているケースが大半です。ここでは、犬が分離不安症になる原因について説明します。
留守番のトラウマ
犬は留守番にトラウマを抱えることで、分離不安症になることがあります。たとえば、長時間放置されたり、留守番中に雷などの恐怖体験をしたりした場合に分離不安症を引き起こしてしまうケースがあります。犬は基本的に留守番をすることができますが、何らかの問題を抱えてしまうと、分離不安症につながってしまうこともあるので注意が必要です。できる限りの配慮をしてあげることで、分離不安症を防ぐことも大切です。
生活環境の変化
犬は、生活環境の変化によっても分離不安症を発症します。何らかの変化があるとそれにスムーズに対応できず、飼い主に頼る気持ちが強くなって分離不安症につながってしまいます。具体的には、引っ越しをしたり、家族が増えたりしたタイミングで分離不安症になってしまう犬もいます。
過剰なしつけ
犬は、過度なしつけを受けた場合にも分離不安症になってしまうことがあります。犬に対するしつけはとても重要ですし、しっかりとしたしつけをして飼い主との関係を理解させる必要があります。しかしながら、それが度を越してしまうと、犬の分離不安症につながってしまうので十分な注意が必要です。過剰なしつけは、本人は気付かずにおこなっていることも少なくありません。客観的に自分自身のしつけを見直してみることも必要です。
もともとの気質や加齢
犬が分離不安症になるのは、もともとの気質が関係している場合もあります。個体差によって、分離不安症になりやすい犬となりにくい犬がいるのは事実です。また、加齢によっても、分離不安症を発症しやすくなるケースがあります。そのため、犬が分離不安症になりにくい性格だからと安心することはできません。いつも犬の様子をしっかりチェックして、何らかの変化が起きたときにはきちんと見極めができるようにしておきましょう。
分離不安症になったら?
気を付けていても、犬が分離不安症になってしまうことはあります。犬が分離不安症になってしまった場合、飼い主はどのような行動を取ればいいのでしょうか。基本的に、軽度の分離不安症であれば、しつけによって解消することが可能です。ただし、飼い主のいうことを聞かないからといって、罰は決して与えてはいけません。罰を与えてしまうと逆効果になることも少なくないため、ゆっくりと経過を見守るようにしましょう。状況によっては、専門家やプロに頼ることも検討したほうがよいです。慣れない状態で犬の症状に対処しようとすると、上手くいかないこともあります。確実に素早く状況を改善するためにも、頼れる人を頼りにしましょう。
分離不安症の予防・対策
犬の分離不安症を予防したり対策したりするためには、どのような方法を取ればいいのでしょうか。犬の分離不安症を防ぐには、いくつかの方法を取り入れることが効果的です。まず、留守番中の環境を整えてあげましょう。飼い主がいなくても安心できる環境を整備することが大切です。また、犬に留守番を覚えさせるときは、いきなり長時間の留守番をさせるのではなく、短い時間の留守番から始めて慣れさせることが必要です。そうすれば、犬も「留守番はこわくない」と理解することができます。さらに、犬の分離不安症を防止するためには、一緒にいるときもあえて構わないというのもひとつの方法です。これは、1匹で過ごすことに慣れさせることを目的としています。もちろん、スキンシップをとることは重要ですが、メリハリをもたせることが大切です。さらに、実際に出掛けるときは、さりげなく出掛けるようにしたほうがよいでしょう。帰宅する際も、大きな音を立てないようにして帰宅するとよいです。「いってきます」や「ただいま」を言わないようにするのも、分離不安症を防ぐためには重要なポイントとなります。
犬の分離不安症の症状を知ってしっかり対策しょう!
犬の分離不安症は、さまざまなことが原因となって引き起こされます。犬の分離不安症を防ぐには、さまざまな場面で注意が必要です。何気ない普段の行動が犬の分離不安症につながってしまうケースもあるため、いつもおこなっていることを振り返ってみることも大切です。犬のもともとの性格によっても分離不安症を発症する可能性は違うので、それぞれの犬の特性を理解することも重要だといえるでしょう。犬の分離不安症は軽度であれば、しつけですぐに改善することも可能です。重症化する前に気付き、適切な対応をしてあげたほうがよいでしょう。そのためには、普段から犬の様子にしっかりと配慮する必要があります。犬にストレスを与えないようにして、犬の分離不安症を防ぐようにしましょう。
犬の分離不安症の症状
犬の分離不安症の症状は以下の通りです。 ● 吠える・壊す・排せつする ● 過剰な引っかき噛む ● ストレスで体調を崩す こちらを順に解説していきます。
吠える・壊す・排せつする
犬の分離不安症の症状は、主に不安や恐怖から生じる行動で、飼い主が離れると現れます。代表的な症状には、吠える、物を壊す、排せつすることがあります。 まず、吠える行動は特に顕著で、飼い主が外出すると、犬は不安を感じて大声で吠え続けてしまうでしょう。 次に、壊す行動です。 犬はストレスを発散するために、家具や靴などを噛んだり引っ掻いたり、部屋を散らかします。 最後に、排せつすることもあります。 通常はトイレを覚えた犬でも、強いストレスがかかると、室内で排せつをしてしまうことがあるのです。 これは、犬が自分の不安をうまく処理できていない証拠です。 これらの症状は、犬にとっても飼い主にとっても辛い状況を引き起こします。 適切な対策を講じることで、犬のストレスを軽減し、より快適な生活を送る手助けが可能です。
過剰な引っかき噛む
犬の分離不安症の症状として、過剰な引っかきや噛む行動が見られることがあります。 これらの行動は、飼い主が離れたときの不安やストレスを軽減しようとする犬の試みです。 まず、過剰な引っかきについてですが、犬は、ドアや窓を引っかいて飼い主が帰ってくるのを待とうとすることがあります。 この行動は、強い焦燥感からくるもので、周囲の物を傷つけることもしばしばです。 次に、噛む行動ですが、犬は、ストレスを感じると、家具や靴を噛んだり、引き裂いたりすることがあります。 この行動は、犬自身の不安を和らげるためのもので、結果として飼い主にとっては大きな問題となることがあります。 これらの行動は、犬が不安を抱えているサインです。 過剰な引っかきや噛む行動は、犬にとってもストレスの原因となります。 早期に対策を講じることで、犬のストレスを軽減し、より平穏な生活を送る手助けができるでしょう。
ストレスで体調を崩す
犬の分離不安症は、ストレスによって体調を崩すことがある深刻な状態といえます。 飼い主が離れると、犬は強い不安を感じ、その結果としてさまざまな健康問題が引き起こされることがあるでしょう。 まず、ストレスが原因で食欲が低下することがあります。 普段は食べることが好きな犬でも、飼い主がいないときにはご飯を拒否することが続くと、体重減少や栄養不足につながる可能性があります。 また、過度のストレスは消化器系にも影響を及ぼすでしょう。 犬が吐いたり、下痢をしたりする症状は、犬の身体がストレスに対処しきれないサインです。 さらに、ストレスが長期間続くと、免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなることもあります。 健康状態の悪化は、犬の生活の質を大きく損なう要因となります。 このように、分離不安症が引き起こす体調不良は、犬にとって非常に辛いものです。
犬の分離不安症の原因
犬の分離不安症の原因は以下の通りです。 ● 飼い主との強い絆 ● 犬の性格や過去の経験 ● 犬を一人きりにする機会が少ない こちらを順に解説していきます。
飼い主との強い絆
犬の分離不安症の主な原因の一つは、飼い主との強い絆です。 犬は社会的な動物であり、特に信頼する飼い主との関係が深いほど、その人に対して依存する傾向があるので、飼い主が離れると不安や恐怖を感じやすくなるでしょう。 特に、幼少期に十分な社会化が行われなかった犬は、外的な刺激に対して敏感になりやすいです。 飼い主がいない状況に対する耐性が低く、孤独感を強く感じることがあります。 また、過去に飼い主を失った経験がある犬も、再度同じ状況になることを恐れ、分離不安に陥ることがあります。 特に、愛情深く、忠実な性格を持つ犬種は、飼い主との絆が強くなるため、分離不安に悩むことが多いです。 このように、飼い主との強い絆が分離不安症の発症に大きな影響を与えます。 犬の心理的な安定を保つためには、絆を大切にしつつ、適切な環境や練習を通じて安心感を与えることが重要です。
犬の性格や過去の経験
犬の分離不安症の原因には、犬の性格や過去の経験が大きく影響するでしょう。 性格面では、特に敏感で内向的な犬がこの症状を発症しやすく、こうした犬は、環境の変化やストレスに対して敏感に反応しやすく、飼い主が離れると強い不安を感じることがあります。 また、過去に飼い主を突然失ったり、引っ越しを経験した犬は、再度同じ状況に直面することを恐れ、不安を抱えることがあるのです。 さらに、トラウマとなるような出来事を経験した犬も、分離不安症を引き起こすリスクが高まります。 これらの要因が重なり合って、犬が分離不安症を発症することが多いのです。 安心できる環境を整え、少しずつ自立を促すことで、犬の不安を軽減する手助けができます。
犬を一人きりにする機会が少ない
犬の分離不安症の原因の一つに、犬を一人きりにする機会が少ないことがあります。 特に、飼い主が常に犬と一緒にいる生活を送っている場合、犬は孤独を感じる経験が少ないので、飼い主が外出した際に、急に一人でいる状況に直面すると、強い不安や恐怖を感じやすくなります。 また、長時間一緒に過ごすことで、犬は飼い主に対して強い依存心を抱くようになり、その結果、飼い主がいない時間が長くなると、心の安定を失い、様々な問題行動を引き起こすことがあるのです。 さらに、犬が一人でいることに慣れていないと、孤独感やストレスを和らげるための適切な方法を持たない場合が多いです。 これは、犬にとって大きな負担となるでしょう。 このように、犬を一人きりにする機会が少ないことは、分離不安症の一因とされています。対策としては、短時間から徐々に一人でいる練習を行い、犬が安心できる環境を作ることが重要です。
犬の分離不安症の対策
犬の分離不安症の対策は以下の通りです。 ● 犬への依存を減らす ● 独りの時間を徐々に慣らす ● 落ち着く環境を用意する こちらを順に解説していきます。
犬への依存を減らす
犬の分離不安症に対する対策の一つは、犬への依存を減らすことです。 これは、犬が飼い主に過度に依存することを防ぎ、より自立した行動をとらせます。 まず、短時間の離れる練習を行い、犬が一人でいることに慣れさせることが効果的です。 最初は数分から始め、徐々に時間を延ばしていくことで、犬は一人でいることが安全であると理解するようになります。 次に、犬が自分で遊ぶ時間を増やすことも役立ちます。 おもちゃやパズルフィーダーを使うことで、犬が自分で楽しむ時間を持つことができ、飼い主がいなくても不安を感じにくくなるでしょう。 また、犬の自己肯定感を高めるために、新しいトリックやコマンドを教えることも効果的です。 これにより、犬は自分で考え行動する力を養い、依存を減らすことができるでしょう。 これらの対策を通じて、犬への依存を減らし、より安心して一人で過ごせるようになることが期待できます。
独りの時間を徐々に慣らす
犬の分離不安症に対する効果的な対策の一つは、独りの時間を徐々に慣らすことです。 この方法は、犬が一人でいることに対して安心感を持てるようにするために重要です。 まず、短い時間から始めることがポイントになります。 例えば、最初は5分程度の短い時間から犬を一人にし、その後少しずつ時間を延ばしていきましょう。 これにより、犬は飼い主が戻ってくることを理解し、孤独感を軽減できます。 次に、飼い主が出かける際には、特別なおもちゃやおやつを与えると良いでしょう。 これにより、犬は飼い主がいない間も楽しむことができ、ポジティブな体験と結びつけられます。 また、出かける前の準備を少しだけルーティン化し、犬にとって予測可能な状況を作ることも重要です。 例えば、外出する前に特定の行動を繰り返すことで、犬に安心感を与えることができます。 このように、独りの時間を徐々に慣らすことで、犬の不安を軽減し、より安心して一人で過ごせるようになることが期待できます。
落ち着く環境を用意する
犬の分離不安症に対する対策として、落ち着く環境を用意することが非常に重要です。 犬が安心できる空間を整えることで、ストレスを軽減し、心の安定を促すことができます。 まず、犬がくつろげる専用の場所を作りましょう。 快適なベッドやクッションを用意し、静かで人の出入りが少ないエリアを選ぶことで、犬にとっての安全基地となります。 次に、環境にリラックスできるアイテムを加えることも効果的です。 たとえば、飼い主の匂いがついた毛布や衣類を置くことで、安心感を与えることができるでしょう。 また、静かな音楽やホワイトノイズを流すことで、外部の音を和らげ、リラックスしやすい環境を作ることができるのです。 さらに、犬が一人でいるときに遊べるおもちゃを用意することも役立ちます。 特に、知育玩具やおやつが入ったおもちゃは、犬の注意を引きつけ、気を紛らわせる助けになります。 最後に、犬が落ち着いて過ごせるよう、定期的な運動や遊びの時間を設けることも忘れずにしましょう。 落ち着く環境を整えることは、犬の分離不安を軽減するための一歩です。
予防と改善のポイント
予防と改善のポイントは以下の通りです。 ● 犬との適切な絆を築く ● 犬の一人遊びを促す ● 獣医師や専門家に相談 こちらを順に解説していきます。
犬との適切な絆を築く
犬の分離不安症を予防し改善するためには、犬との適切な絆を築くことが重要です。 強固な信頼関係を持つことで、犬は飼い主がいないときでも安心感を感じやすくなります。 まず、日常的に愛情を示すことが大切なので、日頃から犬を撫でたり、遊んだりすることで、愛情を伝え、安心感を与えましょう。 また、ポジティブな体験を多く共有することで、犬は飼い主との時間を楽しいものと認識します。 次に、適切な社会化を行うことも重要です。 さまざまな環境や人、他の犬と接する機会を提供することで、犬は不安を軽減し、より自信を持てるようになります。 基本的なコマンドやトリックを教えることで、犬は自分で考え行動する力を養えることで、飼い主が離れることへの不安を減少させられるでしょう。 最後に、一緒に過ごす時間を大切にしつつ、短時間の「お留守番」練習を行うことで、犬は一人でいることに慣れていきます。 適切な絆を築くことで、犬の心の安定を保ち、分離不安症を予防・改善することができるでしょう。
犬の一人遊びを促す
犬の分離不安症を予防し改善するために、犬の一人遊びを促すことが効果的です。 一人で遊ぶことができるようになると、犬は飼い主がいない時間も安心して過ごせるようになります。 まず、犬が楽しめるおもちゃを用意しましょう。 特に、知育おもちゃやパズルフィーダーは、犬が自分で考えて遊ぶことができるため、集中力を高めるのにも役立ち、飼い主がいない間も楽しむことができます。 また、遊びの時間におやつを使うのも良い方法です。 おやつを隠したり、特別なおもちゃと組み合わせたりすることで、犬は楽しみながら自分で遊ぶことができます。 これにより、一人遊びの楽しさを体験し、自立心を育むことができます。 さらに、犬が一人で遊んでいるときは、飼い主が静かに見守ることが大切です。 これにより、犬は自分のペースで遊ぶことができ、安心感を高めることができます。
獣医師や専門家に相談
犬の分離不安症を予防し改善するためには、獣医師や専門家に相談することが非常に重要です。 専門的な知識と経験を持つ人々からのアドバイスは、犬の状態を理解し、適切な対策を講じるための助けになります。 まず、獣医師に相談することで、犬の健康状態を確認できます。 分離不安症が他の健康問題に起因している可能性もあるため、体調をチェックしてもらうことが重要です。 次に、犬の行動専門家やトレーナーに相談することも有益です。 彼らは犬の行動を観察し、具体的なトレーニング方法や改善策を提供してくれるでしょう。 特に、分離不安症に特化した知識を持つ専門家は、効果的なアプローチを提案することができます。 また、専門家との定期的なコミュニケーションを通じて、進捗状況を確認し、必要に応じてアプローチを調整することが可能です。 これにより、犬の不安を軽減し、より安心できる生活を送れるようになります。 最後に、飼い主自身も専門家からの情報を基に学び、犬との関係を深める努力をすることが大切です。
まとめ
犬の分離不安症は、飼い主がいないと感じる不安から様々な問題行動を引き起こします。 過去のトラウマや環境の変化が原因となることが多いです。 予防や改善には、愛情深い絆を築きつつ、一人遊びを促すことが効果的です。 早期の対策が、犬のストレスを軽減し、より快適な生活を提供する手助けになるでしょう。
- 通信講座のSARAスクール編集部
-
心理カウンセラー資格やリンパケアセラピスト等の体系資格、食育資格などを扱うSARAスクール編集部が運営するコラムです。主に女性向けのキャリアアップやスキル習得を目的とした講座が多く、家事や育児と両立しながら学べる環境が整っています。資格取得を目的とした講座も充実しており、仕事や日常生活に活かすことが可能です。